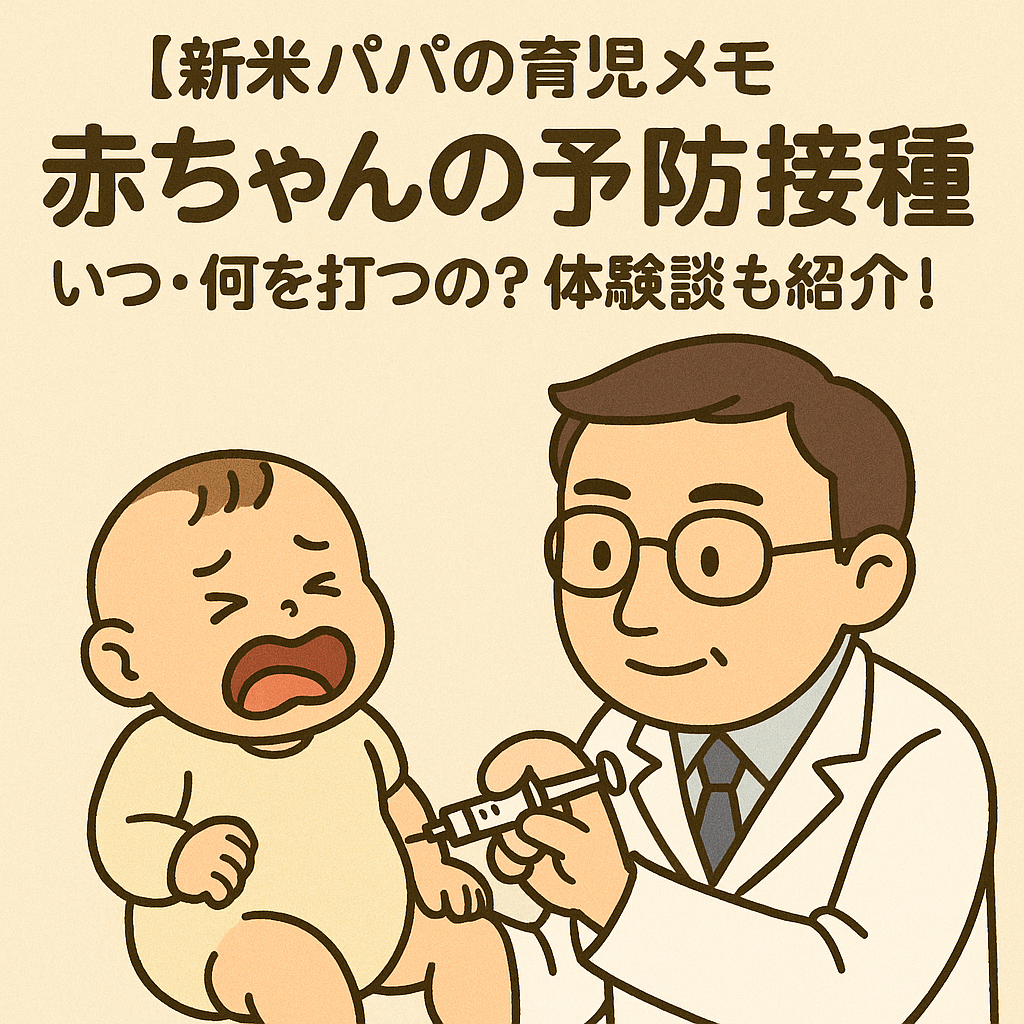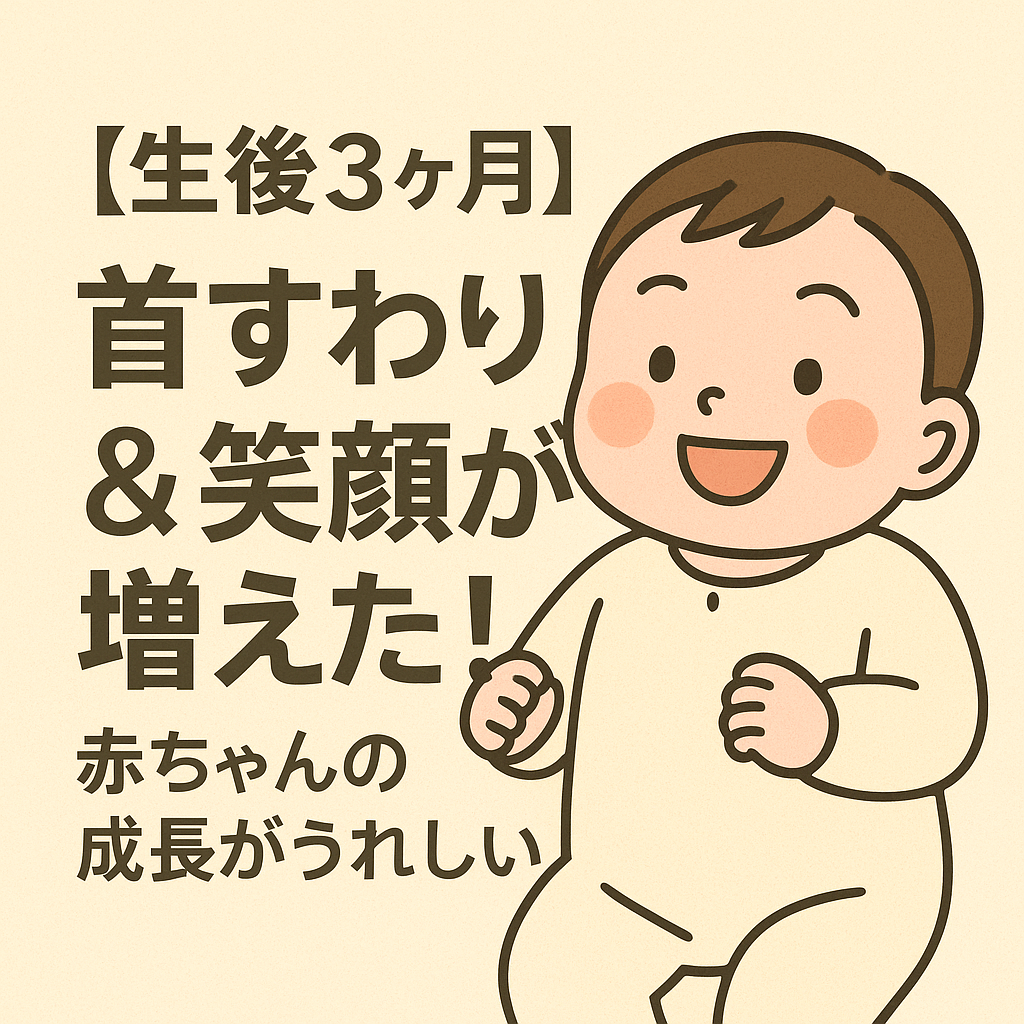赤ちゃんが生まれてから間もなく始まる「予防接種」。スケジュールも多くて、初めてのパパやママには戸惑うことばかりですよね。我が家でも2か月、3か月と予防接種を受けましたが、何のワクチンで副反応って大丈夫なのかと不安だらけでした。
この記事では、僕と同じようにワクチンについて不安な方に向け、いつどんなワクチンを受けるべきか、予防接種の種類やスケジュール、注意点・副反応など、初めての方にも分かりやすくまとめてみました。
1. 赤ちゃんの予防接種の基礎知識
1.1 予防接種とは何か
赤ちゃんの予防接種とは、さまざまな感染症を予防するために、ワクチンを接種して免疫をつける医療行為です。生まれたばかりの赤ちゃんは、母親からもらった免疫によって一部の病気を防ぐことができますが、その免疫は生後数か月で徐々に減少していきます。予防接種は、赤ちゃん自身が特定の病原体に対する免疫を獲得し、重大な合併症や後遺症のリスクを軽減する大切な方法です。
ワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチン、トキソイドなどの種類があり、それぞれ作用の仕方や対象となる感染症が異なります。赤ちゃんが健康に成長するため、市町村などの自治体が中心となり、定期的にワクチン接種の機会を提供しています。
1.2 日本で推奨されている予防接種の種類
日本では、厚生労働省や日本小児科学会の指針に基づき、「定期接種」と「任意接種」に分類された多くのワクチン接種が推奨されています。
以下の表は、赤ちゃん期において日本で推奨される主な予防接種の種類と特徴をまとめたものです。
| ワクチン名 | 種類 | 予防できる主な感染症 | 定期 or 任意 |
|---|---|---|---|
| ヒブワクチン | 不活化ワクチン | 細菌性髄膜炎、敗血症など | 定期 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 不活化ワクチン | 肺炎、髄膜炎、中耳炎など | 定期 |
| B型肝炎ワクチン | 不活化ワクチン | B型肝炎ウイルス感染 | 定期 |
| 四種混合ワクチン(DPT-IPV) | 不活化ワクチン | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ | 定期 |
| BCGワクチン | 生ワクチン | 結核 | 定期 |
| 麻しん風しん混合(MR)ワクチン | 生ワクチン | はしか、風しん | 定期 |
| ロタウイルスワクチン | 生ワクチン | ロタウイルスによる胃腸炎 | 任意 ※2020年10月以降定期接種化 |
| おたふくかぜワクチン | 生ワクチン | 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 任意 |
| インフルエンザワクチン | 不活化ワクチン | インフルエンザ | 任意 |
「定期接種」は法律に基づき市区町村が接種を推奨し、原則として無料で受けられるもの、「任意接種」は自己負担で希望者が受けるワクチンです。しかし、重い感染症を予防し健康な成長を守るため、多くの専門家が任意接種も積極的に勧めています。
これらの予防接種は、集団生活を安心して送るためや社会全体で感染症の流行を防ぐ上でも大きな役割を担っています。適切なスケジュールでワクチンを受けることが重要です。
2. 赤ちゃんの予防接種はいつから始めるのか
赤ちゃんの予防接種は、生後すぐから計画的に開始することが重要です。様々な感染症のリスクが高い新生児~乳児期に、体調や月齢に応じて順番に受けていくことで、重篤な病気を防ぐことができます。予防接種は「生後すぐ始まるもの」「生後2か月から始まるもの」が主にあり、各ワクチンごとに接種時期が決められています。
2.1 生後すぐに受けるべきワクチン
赤ちゃんが生まれてから最初に受けるワクチンは、B型肝炎ワクチンとBCG(結核)ワクチンが主となります。特にB型肝炎ワクチンは、生後すぐ(生後0~2ヵ月)に初回接種を推奨されています。BCGワクチンは地域によって集団接種や個別接種が行われ、生後5ヵ月くらいまでに接種します。これらは母子感染や重症感染の予防に大きな役割を果たします。
| 予防接種名 | 接種開始時期 | 接種目的 |
|---|---|---|
| B型肝炎ワクチン | 生後0~2ヵ月 | 母子感染・ウイルス性肝炎の予防 |
| BCG(結核)ワクチン | 生後5ヵ月までに | 結核の重症化予防 |
2.2 生後2か月から始まる予防接種
生後2か月になると、多くのワクチン接種が始まります。この時期からの予防接種によって、百日せきやインフルエンザ菌b型(ヒブ)、肺炎球菌など、乳児がかかると重症化しやすい感染症から守ることができます。生後2か月のタイミングで複数のワクチンを同時接種することが一般的になっています。
| 予防接種名 | 接種開始時期 | 主な目的と特徴 |
|---|---|---|
| ヒブワクチン | 生後2ヵ月~ | 細菌性髄膜炎、喉頭蓋炎の予防 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2ヵ月~ | 肺炎・中耳炎などの予防 |
| 四種混合ワクチン(DPT-IPV) | 生後2ヵ月~ | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオの予防 |
| B型肝炎ワクチン(2回目) | 生後2ヵ月~ | 1回目接種から間隔をあけて2回目を実施 |
| ロタウイルスワクチン(任意接種) | 生後2ヵ月~ | ロタウイルス胃腸炎の予防。早期開始が推奨 |
これらの予防接種は、接種できる期間が限られている場合もあるため、かかりつけの小児科や自治体から配布される「予防接種スケジュール」を確認し、適切なタイミングですべて受けるようにしましょう。
3. 赤ちゃんの予防接種の種類一覧
赤ちゃんが受けるべき予防接種には、「定期接種」と「任意接種」があります。ここでは、それぞれのワクチンの特徴や対象年齢、副反応などを詳しくご紹介します。
3.1 定期接種のワクチン一覧
定期接種は、感染症の重症化を防ぐために国が実施を推奨している必須の予防接種です。自治体によって公費で受けることができるため、必ずスケジュールに沿って接種しましょう。
| ワクチン名 | 主な対象疾患 | 接種開始時期 | 接種回数 | 主な副反応 |
|---|---|---|---|---|
| ヒブワクチン | ヒブ(インフルエンザ菌b型)による細菌性髄膜炎など | 生後2か月から | 4回 | 発熱、注射部位の腫れ・発赤 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 肺炎球菌による髄膜炎、肺炎、中耳炎 | 生後2か月から | 4回 | 発熱、接種部位の腫れ、機嫌が悪くなる |
| B型肝炎ワクチン | B型肝炎ウイルス感染症 | 生後2か月から | 3回 | 発熱、注射部位の発赤やしこり |
| 四種混合ワクチン(DPT-IPV) | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ | 生後3か月から | 4回 | 発熱、発疹、注射部位の腫れ |
| BCG | 結核 | 生後5か月〜1歳未満 | 1回 | 接種部位の発赤・腫れ、小さな膿が出る |
| 麻しん風しん混合(MR)ワクチン | 麻しん(はしか)、風しん | 1歳、年長時(幼稚園入園前) | 2回 | 発熱、発疹、一時的な関節痛 |
3.1.1 ヒブワクチン
ヒブ(インフルエンザ菌b型)は、乳幼児に重い細菌性髄膜炎などの感染症を引き起こすことがあります。ヒブワクチンは、この重篤な感染症から赤ちゃんを守るために不可欠な予防接種です。スケジュール通り生後2か月から接種を開始しましょう。
3.1.2 小児用肺炎球菌ワクチン
肺炎球菌は、赤ちゃんや高齢者で重症化しやすい病原菌です。細菌性髄膜炎や肺炎、中耳炎の予防に非常に効果的です。3回の初回接種と追加接種1回が必要です。
3.1.3 B型肝炎ワクチン
B型肝炎は母子感染や家庭内感染も懸念されるウイルス性疾患で、肝がんの原因にもなります。赤ちゃんの健康を守るためには、早めの接種が重要です。
3.1.4 四種混合ワクチン(DPT-IPV)
ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオの4つの感染症を1回の接種で予防できるワクチンです。複数回の接種が必要となるため、スケジュールの管理が大切です。
3.1.5 BCG
BCGは、日本では結核を予防するために行われます。赤ちゃんの皮膚に接種痕ができるのが特徴です。生後1歳未満での接種が基本です。
3.1.6 麻しん風しん混合(MR)ワクチン
MRワクチンは麻しんと風しんの2種類のウイルス感染症を同時に予防します。1歳と就学前の2回の接種が必須です。
3.2 任意接種のワクチン一覧
任意接種は、国の定期接種には含まれませんが、赤ちゃんの健康を守るうえで重要な役割を持つワクチンがあります。自己負担となる場合がありますが、感染予防のために積極的に受けることが推奨されます。
| ワクチン名 | 主な対象疾患 | 接種開始時期 | 接種回数 | 主な副反応 |
|---|---|---|---|---|
| ロタウイルスワクチン ※2020年10月以降定期接種化 | ロタウイルス胃腸炎 | 生後6週~生後24週まで | 2回または3回(ワクチンの種類による) | 嘔吐、下痢、発熱、腹部膨満感 |
| おたふくかぜワクチン | おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | 1歳以上 | 2回 | 軽い発熱や耳下腺の腫れ、まれに発疹 |
| インフルエンザワクチン | インフルエンザA型・B型ウイルス感染症 | 生後6か月以上 | 1~2回/年、年齢や接種歴による | 発熱、注射部位の腫れや痛み |
3.2.1 ロタウイルスワクチン
ロタウイルスは冬季を中心に重症の胃腸炎を引き起こし、脱水症状で入院が必要になることもあります。経口ワクチンで、生後早いうちに接種を完了する必要があります。
3.2.2 おたふくかぜワクチン
おたふくかぜは、重症化すると髄膜炎や難聴を引き起こすこともあります。2回の接種で高い予防効果があるため、できる限り受けることが望まれます。
3.2.3 インフルエンザワクチン
生後6か月から接種が可能で、毎年異なる型に対応するため毎年接種します。特に集団生活を始める前に接種すると安心です。
4. 赤ちゃんの予防接種スケジュール
4.1 標準的なスケジュール
赤ちゃんの予防接種は、生後2か月から始まり、決められたスケジュールに沿って進めることが重要です。日本では、多くのワクチンで初回接種時期やその後の追加接種時期が明確に定められています。これに従って接種することで、効果的に感染症から赤ちゃんを守ることができます。
以下の表は、日本国内で推奨されている主なワクチンの接種スケジュール(標準的な例)です。自治体や医療機関によって多少前後する場合がありますので、必ず母子健康手帳やかかりつけ医の指示も確認しましょう。
| ワクチン名 | 接種開始時期 | 接種回数 | 間隔・備考 |
|---|---|---|---|
| ヒブワクチン | 生後2か月 | 4回 | 初回3回(4週間隔)、1年後に追加1回 |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2か月 | 4回 | 初回3回(4週間隔)、1年後に追加1回 |
| B型肝炎ワクチン | 生後2か月 | 3回 | 約4週、20週後に2・3回目 |
| 四種混合(DPT-IPV) | 生後3か月 | 4回 | 初回3回(3-8週間隔)、1年後に追加1回 |
| BCG | 生後5か月まで | 1回 | 標準は生後5か月〜8か月未満 |
| ロタウイルスワクチン | 生後2か月 | 2〜3回 | ワクチンの種類による。遅くとも生後24週まで終了 |
| ※2020年10月以降定期接種化) | 1歳 | 2回 | 初回1歳、2回目は小学校入学前 |
| おたふくかぜ(任意) | 1歳 | 2回 | 1歳、就学前 |
| インフルエンザワクチン(任意) | 生後6か月 | 毎年 | 13歳未満は2回接種 |
スケジュール通りに予防接種を受けることで、赤ちゃんを感染症から早い段階で守ることができます。接種漏れを防ぐため、母子健康手帳などで記録管理をしっかり行い、計画的に進めましょう。
4.2 予防接種スケジュール管理のポイント
赤ちゃんの予防接種スケジュールを管理する際には、いくつかのポイントを押さえておくと安心です。
- 母子健康手帳やスケジュール表に、接種日・次回日程を必ず記録する。
- 同時接種が可能なワクチンは同日にまとめて受けることで、通院回数や赤ちゃんへの負担を減らせます。医師ともよく相談しましょう。
- 一度体調不良などで延期した際は、医師の指示を守りながら適切なタイミングで受け直しましょう。
- 地域ごとに予防接種の案内や無料券の配布など制度が異なる場合があるので、市区町村の保健センターからの案内も必ず確認しましょう。
- 新しいワクチンの定期接種化や推奨年齢の変更など、最新の予防接種情報は定期的に医療機関や自治体の通知をチェックしましょう。
赤ちゃんの体調や生活リズムに合わせて、無理のないスケジュールで進めることも大切です。不安や疑問があれば、必ずかかりつけの小児科医に相談し、安心して予防接種を受けましょう。
5. 予防接種の前後に気をつけること
5.1 接種前の注意点
赤ちゃんの予防接種を安全に受けるためには、接種前の体調管理が非常に重要です。当日は必ず体温を測り、発熱や明らかな体調不良がないかを確認しましょう。通常、37.5℃以上の発熱がある場合は接種できません。
また、普段と異なる様子(機嫌が悪い、食欲がない、便の異常など)がある場合は、必ず事前に医師へ相談しましょう。
アレルギーや既往歴がある場合は、母子手帳や予診票に必ず記入し、医師に伝えるようにしましょう。
予防接種を受ける際には、母子健康手帳、予診票、健康保険証など必要な持ち物を忘れずに持参することも大切です。
| 確認事項 | ポイント |
|---|---|
| 体調チェック | 発熱や下痢、嘔吐、極端な不機嫌等がないかを確認 |
| アレルギー歴・既往歴 | 予診票に記載し、医師に相談 |
| 持ち物 | 母子手帳、予診票、保険証、お薬手帳など |
| 着脱しやすい服装 | ワクチンの接種部位がすぐ出せる服装で来院 |
5.2 接種後の注意点と副反応について
予防接種の後は、急性の副反応に備えて、医療機関で少なくとも30分ほど様子を観察することが推奨されます。接種部位の腫れや赤み、発熱、機嫌の悪さは比較的よく見られる副反応ですが、たいていは数日以内に自然に改善します。
万が一、接種後に高熱(38.5℃以上)やけいれん、呼吸困難、全身のじんましんなどの異常症状があらわれた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
接種当日は激しい運動や入浴を控えることが一般的ですが、38℃未満の微熱や機嫌が良好な場合は、普段通りの生活で問題ありません。ただし、当日の入浴は、接種部位をこすらないように軽めに行いましょう。
| 副反応の主な症状 | 対応・経過観察ポイント |
|---|---|
| 接種部位の腫れ・赤み・硬結 | 数日様子をみる。ひどくなる、膿が出る場合は受診 |
| 発熱(38.0℃未満) | 多くは24~48時間で改善。水分や睡眠を十分にとる |
| 全身反応(高熱・けいれんなど) | 直ちに小児科受診、緊急時は救急へ |
| 日常生活への影響 | 機嫌が良ければ普段通りでOK。心配な場合は医師相談 |
副反応について気になることがあれば、遠慮なくかかりつけ医や予防接種相談窓口に問い合わせましょう。
6. 接種を受けられない場合や特別なケース
6.1 体調不良時やアレルギーがある場合
赤ちゃんが発熱や体調不良を伴っている場合には、予防接種は見合わせるのが一般的です。特に37.5℃以上の発熱や、激しい咳、強い下痢、嘔吐などが認められる際は、医師の診察を受けてから判断しましょう。アナフィラキシーなど重いアレルギー反応を過去に起こした経験がある場合や、ワクチンに含まれる成分(ゼラチンや卵、抗生物質など)に対するアレルギーが判明している場合も接種を控える必要があります。
| 接種を控える主なケース | 具体例 | 注意点・対策 |
|---|---|---|
| 発熱 | 37.5℃以上の熱があるとき | 解熱後、体調が回復してから医師に相談 |
| 急性疾患 | 咳、下痢、嘔吐、インフルエンザ、溶連菌など | 症状が治まった後に接種を検討 |
| アレルギー | ワクチン成分や薬剤へのアレルギー | 該当ワクチンの接種は回避または専門医に相談 |
| 過去の重い副反応 | アナフィラキシーやけいれんなど | 必ず医師へ詳細を伝える |
接種当日は、予診票で健康状態や既往歴、家族のアレルギー歴もしっかり伝えてください。
6.2 兄弟がいる場合の注意点
複数の子どもがいる場合、家庭内感染症が疑われるときや流行している時期は、特に注意が必要です。例えば上の兄弟が感染症にかかっている場合、乳児が感染するリスクを避けるため予防接種の日程を調整することをおすすめします。
また、兄弟姉妹と同日に予防接種を受ける場合は、付き添い者が一人で同時に複数人を管理するのは大きな負担となるため、十分な体制を整えるか、日をずらして受けることを検討しましょう。副反応が起きた際の対応も想定し、なるべく安全かつ安心な方法を選択してください。
6.3 その他の特別なケース
基礎疾患(先天性心疾患、免疫不全など)や特殊な医療処置(長期入院、特殊な治療中など)がある赤ちゃんも、かかりつけ医の判断に従う必要があります。特定のワクチンについて接種が制限されるケースや、接種時期を遅らせたり再検討したりすることもあります。
また、早産児や低体重児の場合も、主治医による個別の接種スケジュール調整が必要です。一般と同様の時期から接種開始できることが多いですが、一部注意が必要な場合もあるため必ず医師に相談しましょう。
| 特別なケース | 考慮される点 | 主な対応 |
|---|---|---|
| 基礎疾患がある場合 | 心疾患・腎疾患・免疫不全など | 専門医の指示に従う |
| 早産・低体重児 | 体調や発育状態を踏まえた判断 | 原則、生後2か月から接種可能だが主治医と相談 |
| 長期入院中 | 感染管理・体調管理が重要 | 入院先で主治医の相談のもと接種計画 |
予防接種は赤ちゃんや周囲の健康を守る大切なものですが、安全に受けるためには個別の事情をよく考慮し、医師や医療スタッフと協力しながら進めましょう。
7. よくある質問と回答
7.1 予防接種と発熱の関係
赤ちゃんが予防接種を受ける際、発熱している場合は接種を延期することが基本的なルールです。通常、37.5℃以上の発熱が認められるときは、安全のため予防接種を見送ることになります。ただし、平熱に戻れば、多くの場合は再度受けることが可能です。
また、予防接種の後に発熱することもありますが、これはワクチンに対する免疫反応であり、通常は一時的な副反応です。ほとんどの発熱は24~48時間以内におさまりますが、高熱やぐったりしている様子が見られた場合は、医療機関へ相談しましょう。
7.2 予防接種を複数一度に受けて大丈夫か
赤ちゃんの予防接種は、医師の判断のもとで同時接種が可能です。同時に複数のワクチンを受けることで通院回数を減らすことができ、病気のリスクを早期に下げるメリットがあります。日本小児科学会でも同時接種を推奨しています。
表にて、同時接種が可能なワクチンの例をまとめました。
| ワクチン名 | 同時接種の可否 | 注意点 |
|---|---|---|
| ヒブワクチン | 可能 | 副反応は個人差あり |
| 小児用肺炎球菌ワクチン | 可能 | 他ワクチンと同時接種推奨 |
| B型肝炎ワクチン | 可能 | 赤ちゃんの健康状態を確認 |
| 四種混合ワクチン | 可能 | 接種部位や本数に注意 |
| ロタウイルスワクチン | 可能 | 経口接種のため吐き戻しに注意 |
同時接種によって副反応が増すことはなく、安全性にも問題はありません。ただし、体調や持病などにより医師が判断する場合もあるため、必ず事前に相談してください。
7.3 接種を忘れた場合の対処法
予防接種を受ける予定日を過ぎてしまった場合でも、スケジュールを修正して接種を続けることが大切です。接種間隔が空いてしまうと、十分な免疫がつかない可能性がありますが、途中からでも再開することで効果があります。
自己判断でやめたりせず、母子健康手帳を持参し、小児科やかかりつけ医に相談してください。必要に応じて、医師が最適なスケジュールを調整し直してくれます。
また、行政の予防接種担当窓口や、予防接種予診票に記載されている連絡先に問い合わせるのもおすすめです。特に、定期接種は自治体が定める期間内であれば公費で受けられるため、なるべく早めに受けましょう。
8. まとめ
赤ちゃんの予防接種は、重い感染症から守るためにとても重要です。スケジュールに従い、定期接種と任意接種の違いを理解したうえで、ヒブや四種混合、ロタウイルスなどの各ワクチンを適切な時期に受けましょう。体調やアレルギーなど不安があれば、必ず小児科医に相談し、安全に予防接種を進めることが大切です。
9.我が家の体験談
うちの子は初めてと2回目の予防接種で大泣きでした。3本の注射と経口ワクチンと大人でも嫌ですよね・・・
終わった後は、なだめるのに一苦労しました。
でも、その後は熱も出ず、機嫌もいつも通りだったので安心しました。
ロタウイルスワクチン接種後は、胃腸炎になる可能性があるとのことで、おむつ替えのあとの手洗いを徹底しました。